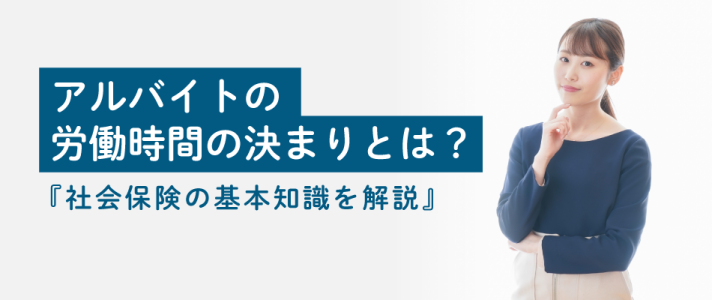アルバイトの労働時間の決まりとは?社会保険の基本知識を解説
- アルバイトでも、残業をすることがあります。ただし、ルールがあり労働時間によっては、社会保険の加入対象になるため注意が必要です。
本記事では、アルバイトにおける労働時間の決まりを解説します。社会保険に加入する条件や加入しないための方法など、ぜひ参考にしてください。
- アルバイトの労働時間には決まりがあります。ここでは、労働時間の種類や36協定などについて解説します。
- 労働時間には2つの種類がある
労働時間は、以下の2つに分類されます。
・法定労働時間:労働基準法第32条によって規定されている労働時間の限度(1日8時間、週40時間)
・所定労働時間:労働者が労働の義務を負う時間。始業時間から終業時間までの時間から休憩時間を差し引いたもの
たとえば、9時始業で17時終業、休憩時間が1時間という場合の所定労働時間は7時間です。
- 法定労働時間を超える場合は36協定の締結が必要
法定労働時間を超える労働を課す場合には、36協定の締結が必要です。36協定とは、労働基準法第36条に基づいて労使間で結ばれる労働時間などに関する協定です。時間外労働を行う場合には、アルバイト先との間で36協定を締結しなければいけません。ただし、例外となるケースもあります。次項では例外となるケースを解説します。
- <例外になるケースもある>
時間外労働をする場合は原則として36協定の締結が必要ですが、特定の業種で、かつ常時10人未満の従業員が働く職場は「特例措置対象事業場」となり、法定労働時間の例外となります。この場合1日8時間、週44時間までの労働が認められます。特例措置対象事業場は以下のとおりです。
・小売業
・理美容業
・病院
・飲食店
・卸売業
・旅館
・社会福祉施設など
ただし、特定の業種であったとしても18歳未満は対象外です。
- <特別条項付き36協定との違い>
時間外労働をするには36協定を締結しなければいけません。しかし、36協定を締結したからといって、制限なく時間外労働をさせられるわけではありません。36協定を締結した場合、月45時間年36時間までの時間外労働が認められます。これ以上の時間外労働は違法となるため注意しましょう。
しかし、繁忙期などで残業が多くなるケースもあります。繁忙期に対応する際には、特別条項付き36協定をアルバイト先と締結します。特別条項付き36協定を締結することで、1か月100時間未満、年720時間以下の時間外労働が可能です。
法定労働時間を超えてアルバイトが働く場合の賃金とは
- アルバイトが残業する場合、賃金はどうなるのでしょうか。ここでは、アルバイトが残業する際の賃金について解説します。
- 割増賃金が発生する
法定労働時間を超える労働をした場合には、割増賃金が発生します。
・法定労働時間を超えた時間外労働:通常時給×1.25以上
・22時から5時前の深夜労働:通常時給×1.5以上
割増賃金が発生するのは、あくまでも法定労働時間を超えた場合です。
- 残業時間には上限が設定されている
従来は残業時間に上限はありませんでした。しかし、労働基準法が改正されて、原則月45時間、年360時間という上限が設けられています。大企業では2019年4月から適用されており、中小企業でも2020年4月から適用されているルールです。
特別な事情がある場合でも、以下のような規定に従わなければいけません。
・1か月で100時間未満
・年間720時間以内
・複数月の平均労働時間が休日労働含めて80時間以内
・45時間以上の労働月は年間計6か月以内
アルバイト先が残業時間のルールを守らないと罰則が科せられる
- アルバイト先が残業時間のルールを守らずに過剰に残業させていた場合などは、罰則を科せられる可能性があります。主な罰則の例は以下のとおりです。
・36協定を締結せずに残業させた: 6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金
・残業時間の上限を超える残業をさせた:6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金
また、厚生労働省が企業名を公表するケースもあり、社会的な信頼を失ってしまう恐れもあります。36協定を締結していないのに残業をさせられるなどの問題があった場合には、必要に応じて労働基準監督署へ相談しましょう。
労働時間が長いと社会保険の加入対象になる可能性がある
- 労働時間が長くなると、社会保険の加入対象となる可能性があるため注意が必要です。社会保険の適用拡大が進められており、アルバイトであっても社会保険の加入対象になるケースがあります。ここでは、社会保険の加入対象となる条件について詳しく解説するため、社会保険への加入を防ぎたい場合は参考にしてください。
- 条件1:所定労働時間
週の所定労働時間が20時間以上の場合は、社会保険の加入対象となります。所定労働時間には残業や休日出勤などの時間外労働は含まれません。ただし、労働契約のうえでは、所定労働時間が20時間未満となっていた場合でも、社会保険に加入することになるケースがあります。実際の労働が20時間以上の状態が2か月を超え、同じ状況が続くことが見込まれる場合、3か月目から社会保険に加入する必要があるため注意してください。
- 条件2:雇用期間
雇用期間が2か月を超えることが見込まれる場合には、加入対象となります。雇用期間の条件は2022年10月の改正により見直され、新基準となりました。改正前は1年を超える雇用が見込まれる場合となっており、条件が大幅に変更されています。
- 条件3:月額賃金
月額賃金8万8,000円以上の場合も社会保険の加入対象です。月額賃金とは、基本給に諸手当がプラスされたものを指します。月額賃金に含まれないものとしては、以下が挙げられます。
・時間外労働の割増賃金
・賞与
・通勤手当や家族手当などの最低賃金に参入したいことが決められている賃金
- 条件4:学生でない
学生ではないことも条件となります。学生は社会保険の加入対象外となるため、高校生や大学生、専門学校生などは上記の条件をすべて満たしていても対象外となります。ただし、休学中の学生や内定者など、継続した勤務が見込まれる学生は加入対象です。
- 適用拡大前と適用拡大後の違いまとめ
社会保険の適用拡大前と適用拡大後の違いを表にしてまとめました。
- このように、適用される事業所の従業員数が大幅に緩和されており、多くの事業所が対象となりました。また、見込み雇用期間も大幅に短縮されています。
社会保険に加入するとどうなる?加入したくない場合の対応方法とは
- 社会保険に加入したくないと考えている人もいるでしょう。ここでは、社会保険に加入したくない場合の対応方法を解説します。
- 社会保険に加入するとどうなるのか
社会保険に加入することで、将来受け取れる年金が増える、事故や病気などで障害が出た場合に障害厚生年金が支払われるなど、受けられる保証が手厚くなることは大きなメリットです。また、保険料の半分を事業者に負担してもらえるため、自己負担が軽く済みます。
ただし、社会保険に加入すると保険料の支払いが必要です。収入から社会保険料が差し引かれるため、手取りが少なくなります。
- 社会保険に加入したくない場合の対処方法
社会保険に加入したくない場合には、労働時間を調整しましょう。労働時間が長くなることで月額賃金も多くなり、社会保険の加入条件を満たしやすくなります。そのため、労働時間を抑えるのが効果的です。また、1か月未満の短期アルバイトをする、非該当の事業所でアルバイトをするといった方法もあります。
- アルバイトの労働時間では、注意したいポイントが5つあります。ここでは、各注意点を詳しく解説します。
- 注意点1:法定内残業
法定内残業とは、法定労働時間(1日8時間)を超えない残業のことです。法定労働時間を超えない場合は残業しても割増賃金は発生しません。法定労働時間を超えた場合は、時間外労働の割増賃金がプラスされます。
- 注意点2:休日手当
休日手当とは、法定休日に働いた際に支払われる手当のことです。法定休日とは週1日もしくは4週間を通じて4日以上と決められており、法定休日に働いた場合は通常時給×1.35という休日手当が支払われます。
- 注意点3:深夜手当
深夜手当とは、原則午後10時から午前5時の間の労働に支払われる割増賃金です。通常の時給に25%割増した賃金が支払われます。法定労働時間を超えており、午後10時以降の残業をした場合には、「時間外手当(25%)」と「深夜手当(25%)」の双方が発生するため、50%の割増賃金が発生するという仕組みです。
- 注意点4:アルバイトの掛け持ち
なかにはアルバイトを掛け持ちしたい、実際に掛け持ちしているという人もいるでしょう。法定労働時間は、1つの事業所での労働時間ではなく、すべての事業所での合計労働時間で計算されます。所定労働時間によっては割増賃金が発生することがあるため、アルバイト先ごとに労働時間をきちんと把握しておく必要があります。
- 注意点5:休憩時間
どんなに忙しくても、アルバイトも休憩時間は必須です。休憩時間は労働時間によって規定されています。
・労働時間6~8時間:休憩時間45分以上
・労働時間8時間以上:休憩時間60分以上
労働時間の合間に休憩を取らず、早上がりするというケースもあるでしょう。しかし、このケースでは休憩時間を取ったことにはならないため注意が必要です。
バイトの休憩時間についての記事はこちら
- アルバイトにも労働時間のルールがあります。原則として、36協定を締結しなければ時間外労働はできません。また、労働時間が長くなると社会保険の加入対象になる可能性もあります。社会保険へ加入したくない場合には、労働時間を抑える、短期のアルバイトをするなど工夫しましょう。
シフトワークスは、時間やシフトから自分に合った仕事を探せるアルバイトサイトです。自分の都合に合わせた時間や曜日から検索できるため、短時間のアルバイトを探している場合にもよいでしょう。スキマ時間を有効活用してアルバイトがしたいという場合は、ぜひご活用ください。