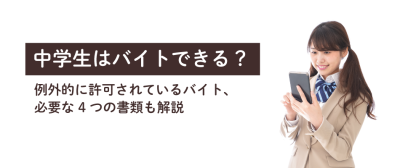中学生はバイトできる?例外的に許可されているバイト、必要な4つの書類も解説
- 中学生でもバイトができるのか、気になっている人もいるのではないでしょうか。この記事では、中学生はバイトができるのか、例外的に許可されているバイト、バイトをする際に必要な4つの書類など、中学生のバイトに関する疑問を解説します。ぜひ参考にしてください。
- 中学生のバイトは、労働基準法により原則禁止されています。労働基準法第56条で、「満15歳に到達した日以後、最初の3月31日までは労働してはいけない」と定められているからです。満15歳に到達するのは中学3年生の年なので、中学生の間は労働してはいけないことになります。
ただし、肉体的な負担がかからない簡単な仕事であれば、例外的に認められるケースがあります。その場合は、周囲の許可を得た上で、学校のない時間に働くことが可能です。
※参考:労働基準法 | e-Gov法令検索
- 中学生でも例外的に許可されるバイトには、新聞配達やキッズモデル・子役があります。
- 新聞配達
新聞配達は、担当エリアで契約している家庭に朝刊や夕刊を配達する仕事です。中学生は運転免許を取得できないため、歩いたり自転車を使用したりして配達します。
ただし、労働基準法では、中学生が働ける時間を午前5時から午後8時までとしています。まだ暗いうちから配達し始める朝刊に対応するのは時間的に難しいので、中学生がバイトをする場合は夕刊の配達となるでしょう。中学生を受け入れているかどうかは、会社によっても異なります。
- キッズモデル・子役
キッズモデルや子役など、芸能関係の仕事も条件を満たしていれば可能です。中学生が働ける時間帯は通常午後8時までですが、芸能関係の仕事の場合は、午後9時まで可能とされています。
仕事の内容は、折り込みチラシや商品パッケージのモデル、雑誌、CM出演などです。キッズモデルや子役のバイトをする際は、まず芸能事務所などに所属することから始めます。また、芸能事務所に所属すれば必ず仕事が入るわけではないという点に注意しましょう。
- 中学生がバイトをする際は、身分を証明する戸籍証明書のほか、周囲の人の同意書などが必要です。
- 1.戸籍証明書
年齢を証明するために戸籍証明書を提出します。戸籍証明書とは、出生してから死亡するまでの身分を公に証明するためのものです。戸籍証明書には、戸籍に記載されている全員分を記した全部事項証明(戸籍謄本)や、本人分のみを記した個人事項証明(戸籍抄本)、必要な事項のみを証明する戸籍一部事項証明などがあります。
戸籍のある市町村の役場で発行できるほか、マイナンバーカードを持っている場合は、近所のコンビニエンスストアで発行することも可能です。発行する際は、発行手数料がかかります。
- 2.親権者または後見人の同意書
労働基準法第57条では、未成年を雇う会社は親権者または後見人の同意書を事業場に備え付けることを義務としています。そのため、中学生は親や祖父母などの親権者もしくは後見人の同意書を提出しなければなりません。バイトをする際は親権者や後見人とよく相談し、同意してもらった上で働きましょう。
なお、労働基準法第58条では、「親権者または後見人が、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない」としています。
※参考:労働基準法 | e-Gov法令検索
- 3.児童使用許可申請書
児童使用許可申請書とは、雇い主となる会社が労働基準監督署に提出しなければならない書類のことです。労働基準法で原則として働くことが認められていない「満15歳に達した日以降で、最初の3月31日が過ぎていない未成年」を雇う場合に提出します。
児童使用許可申請書は本人の情報や労働条件を記載する書類で、労働基準法に違反していないことを証明するために必要です。会社はこの書類を作成・提出し、労働基準監督署長から許可を得ます。
- 4.学校長の証明書
中学生がバイトをする場合は、通っている中学校の校長先生に証明書を発行してもらう必要があります。「バイトをしても学業に支障はない」と証明するために必要な書類です。この書類は児童使用許可申請書と一緒に労働基準監督署に提出しなければなりません。
親権者や後見人だけでなく、校長先生にもバイトをしたいことを相談し、許可を得ましょう。校長先生のほか、担任の先生など関わっている先生にも相談しておくと安心です。
- 中学生がバイトをできる時間帯は、原則として午前5時から午後8時までです。芸能関係の仕事の場合は特別に午後9時まで認められます。厚生労働大臣が必要と許可した場合に限り、場所や期間を限定して午前6時から午後9時までバイトをすることも可能です。
また、労働基準法60条2項において、働ける時間も決まっています。中学生が働けるのは、修学時間と通算して週に40時間以内かつ、1日7時間以内です。修学時間は授業を受けている時間であり、お昼休みや休憩時間は含めません。
働ける時間が限られているのは、「義務教育期間中である中学生は、仕事よりも学業を優先しなければならない」という考え方があるからです。
※参考:労働基準法 | e-Gov法令検索
- 中学生が働いて得たバイト代は、本人が受け取らなければなりません。労働基準法24条1項では、「賃金は労働者に直接支払わなければならない」と定められているからです。さらに、労働基準法59条では、未成年でも賃金の請求権を持っているとし、親権者や後見人が賃金を受け取るのを禁止しています。
※参考:労働基準法 | e-Gov法令検索
- 中学生でバイトを始めたい場合は、自分だけで判断してはいけません。事前に保護者や先生など、周囲の大人に相談することが大切です。働きたい理由や、いつどのようなタイミングで働くのか、学業や部活はどのように対応していくのかなどを相談しましょう。
バイトを始めてからも「決められていた時給と違う」「辞めたいのに認めてもらえない」など、問題が発生したときは、一人で悩まず保護者や役所に相談しましょう。
- お金を稼ぐ方法は、バイトだけではありません。中学生がバイトをしなくても稼げる方法はいくつかあります。
- 家の手伝いをしてお小遣いをもらう
中学生がバイト以外で安心してお金を得られる方法が家の手伝いです。たとえば、料理や配膳、片付け、掃除、洗濯など、保護者が日常的にしている家事です。
自宅にいながらできるだけでなく、中学生のうちから始めておけば、早い段階から家事スキルを上げられます。高校生や大学生になってからバイトを始めたときに、料理や掃除などのスキルが役立つこともあるでしょう。家庭菜園の世話や日曜大工、洗車の手伝いなど、屋外の手伝いもおすすめです。
- フリマアプリで使わなくなった物品を売る
フリマアプリで使わなくなった物品を売ってお小遣いを稼ぐ方法もあります。近年はさまざまなフリマアプリが提供されており、利用者も増えています。読み終わったマンガ本やゲーム、サイズアウトした洋服など、部屋の整理を兼ねて探してみましょう。保護者に確認して、家の中の不用品を売らせてもらうことも一つの方法です。
ただし、フリマアプリを利用する際は、自分のものでも売る前に必ず保護者の許可を得てから出品しましょう。
- ポイントサイトやアンケートモニターを活用する
ポイントサイトは、指定されたサイトにアクセスまたはアプリのダウンロードでポイントを貯め、ある程度貯まったら換金できるサイトです。また、アンケートモニターは、さまざまな会社が実施しているアンケートに答えると謝礼金がもらえます。定期的に収入が得られるとは限りませんが、コツコツ積み重ねるとある程度まとまった収入が得られます。
無料で登録できるサイトがほとんどですが、詐欺などのトラブルに巻き込まれないためにも、運営会社や口コミを調べてから利用しましょう。
- 中学生は原則として、バイトが認められていません。ただし、新聞配達やキッズモデル・子役などの芸能活動で収入を得ることは可能です。バイトを始めたい場合は自分一人で進めるのではなく、保護者や先生、状況によっては役所などに相談しましょう。定期的にまとまったお金が入るわけではありませんが、家の手伝いなどで収入を得ることも可能です。
高校生になり、本格的にバイトをしたいと考えている場合は、シフトワークスを利用することがおすすめです。シフトワークスは時間やシフトから仕事探しが可能で、高校生歓迎などの条件から探すこともできます。バイト探しを始める場合は、シフトワークスをチェックしてみましょう。